魔王の自覚があるのか、と問われて、「ある」と答えたことはなかった。なぜなら、魔王にとって魔族は、つい最近まで競り合ってきた相手だったからだ。ある日突然勇者だともてはやされ、言われるままに魔族を退けてきた元勇者。それが魔王の正体だ。
魔王となって日の浅いうちは自らの身の危険を考えて勇者には徹底抗戦の構えでいたが、それぞれの土地で暮らしていたはずの魔族が殺されていく状況に嫌気がさし、魔王は魔族たちを召集した。軍隊をつくろうとしたわけではない。ただ籠城のように、城の周りを片付け、街をつくり、のどかな時間を過ごすようにした。魔王ともあろう者がなにを弱気な、と反対する者もいたが、賛同者だけで豊かな箱庭をつくるのは魔王にとって有意義な時間だった。
「やはり勇者が勝つというのは変わらないものなのか……」
魔王になってすぐ、決断を頼み込んだ親友はここにはいない。ちょっとした一言でも拾われていたせいか、独り言が長い時間漂っているように思える。
親友が街に辿り着いた勇者を追い払おうとして死んだのは、ついさっきのことだ。これまでも勇者を街から遠ざけようと奮闘していたが、正面切っての戦いは無謀だった。魔王は親友がつくってくれた時間で街にいた魔族たちを魔力で隠すことができたものの、世の非常さに奥歯をギリギリと噛みしめた。
「俺が初めてここへ来たときも、魔王はこんな気持ちを抱いていたのか……?」
ゆっくりと兜を被り、面甲を下ろす。いつか今日が来ることはわかっていたが、それでも魔王は親友の死だけは受け入れられずにいた。仲間がいなかった元勇者にとって、親友は最初で最後の親友だった。
力を抜いて王座に座ると、バタバタと走る音が聞こえてきた。もう時間はない。
「まったく、やかましい」
魔王はこの先をいやと言うほど知っている。だからこそ、親友の死に対する悲しみも、これまでの日々の楽しさも、ようやく終われることへの安堵も、すべて鎧の外に見せることなく、ただ眼前に現れた勇者に呪いを吐く。
「世界の半分をお前にやろう」
酷く曖昧な世界
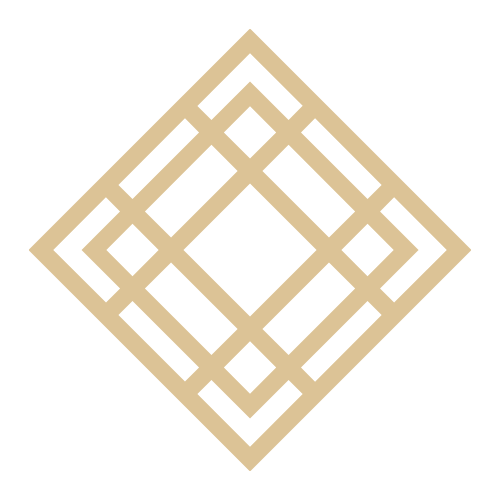 短編
短編