死刑執行。言葉にすると、その短さに対して重すぎる意味がのしかかる。執行時は複数人で同時にダミーを含めたボタンを押すから、必ず刑は執行される。でも、もし押すタイミングが少しだけ遅くて、自分か押すボタンによって執行されると気づいてしまったら、……。
「貴方の意見は変わりませんね。どうして執行官になったんです? 政治や司法を動かすような仕事に就いた方が良かったと後悔することはないんですか?」
「随分直接的に訊きますね」
「おや、失礼。きちんと聞いてみたいと思ったのです」
上長に呼ばれて部屋に入ると、予想していた通りの面談が始まった。最近の調子はどうか、精神的に堪えていないか、食事は摂れているか……いつもと変わらない内容だった。そして、最後にお互い自由に話しているうちに極刑とはなにか、という話題になった。
極刑。すなわち死刑だ。受刑者には首を括ってもらい、床が開くことで自重によって首の骨が折れ死に至る。よほど首が頑丈でないかぎりは楽に死ねる方法らしい。しかし私は死刑を極刑だとは思っていない。なぜならほぼ一瞬で死ねてしまうからだ。どんな極悪非道を犯した人でも、ほとんど苦しまずに死んでしまう。私はそれが許せない。心を改めているのならまだしも、死刑宣告後にへらへらと日々を過ごした人が、なぜ楽に死ねるのか。
この気持ちを初めて吐露した相手が、今目の前にいる上長だ。仕事中は同じ執行官でも怖くてたまらないが、こうした面談やプライベートでは敬語で、しかも柔らかに話すため最初はギャップに戸惑ったことをよく覚えている。死刑じゃ許せない、と言ったときも、上長はただ「それが貴方の正義感の根本かもしれませんね」と否定することはなかった。だから、改めて死刑制度そのものを変える職業について話を振られるとは思ってもみなかった。
「私にとっては制度を変えるよりも、実際に受刑者と接することの方が大事だったというか……許せないからこそ、その内側にいようと思ったのだと思います。外側から知らない現場をかき乱すのはどうかと」
「なるほど? う~ん、その気持ちもやっぱり貴方の正義感っぽいですね」
上長はうんうんと頷くと、ちらりと時刻を確認して姿勢を正した。
「あまり長居させるわけにもいかないので、今回の面談はここまでにしましょうか。話したりないことなどあれば適当に呼んでください」
「はい。ありがとうございました」
「それと、食事はきちんと摂ってくださいね。あまり言いたくなかったのですが、目に見えて痩せてきていますよ。辛ければ仕事量の調整もしますから、」
「いえ、それには及びません。大丈夫です、失礼します」
そそくさと逃げるように部屋を出た。ふう、と一息ついてから業務へ戻る。
痩せてきているのは、実際に食べていないからだ。数週間前に、自分が押したボタンによって死刑が執行されたことに気づいてしまった私は、「人を殺す権限」を持っていることに優越感を持ってしまった。執行官として到底許されることではない。だから日々少しずつ食べる量を減らして、昨日からは水しか飲んでいない状態だ。
私は死刑を極刑だとは思っていない。終身刑、それも食事や運動などの人間的な暮らしが保証されるものではなく、ただ暗所でなにも与えられず朽ちていくだけの終身刑こそが極刑だと思うのだ。だから私は私に極刑を与えることにした。さすがに仕事があるためずっと薄暗い場所に閉じ籠ることは難しいが、それでもこうして身体を衰弱させることはできた。あとは長期休暇をとって、自室に籠るだけだ。周囲の目が届かなければ無理やり病院に送られることもないだろう。飲み食いせず、死ぬ。私が回りに手を出し、助けを求めなければこの極刑は執行できる。
自ら人を殺すという行為に価値を感じてしまったのだから、執行官に処されるのが法治というものだろう。
正義
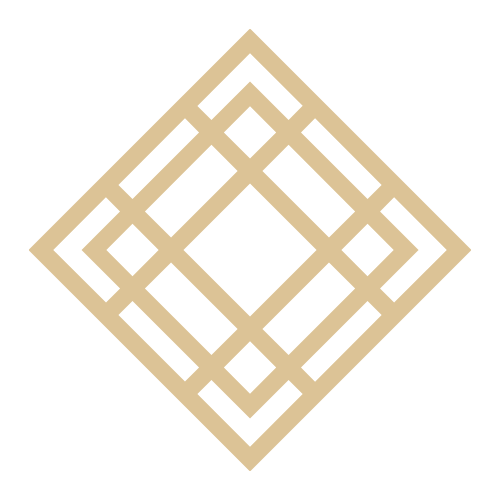 短編
短編