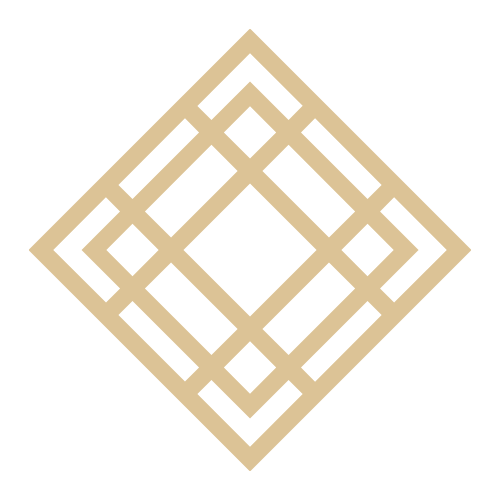平穏な街の往来には似合わない、鍔迫り合いの嫌な音がする。普段の賑やかさは鳴りを潜め、夕暮れの街は静かに揉め事の中心地を見つめていた。
短剣を手にした大柄な男は苛立った様子で、包丁で応戦している男を睨み付けた。
「さっさとそのガキが持ってる笛をよこせ!」
「それはできない相談だな。この子は明らかにお前に怯えているし、そもそも往来で刃物を出すような輩は一軍人として見過ごせないからね」
私服の自称軍人はそう言って、ちらりと後ろを確認した。子どもは座り込んで震えている。まだ十歳に満たない、戦時を知らない子どもだ。刃物を突きつけられるのはおろか、身近に軍人がいなければ武器として扱われる刃物を間近で見たこともないだろう。
揉め事の発端を自称軍人は知らない。悲鳴を聞いて駆けつけたときには、男が子どもに短剣を向けていたからだ。レストランの店先でおろおろとしていた店主から包丁を借りた自称軍人は応戦しながら、子どもが男から何かを奪ったらしいと聴いた。しかし、それがいったい何なのかを伝えずただ暴力に訴えているのであれば、収めるべきは子どもではなく大人の方だ。
慣れない得物で子どもを後ろに守る自称軍人は防戦一方になりつつあった。男はそれに気づき、相手が避けないと見越して突進した。しかし、その鋒が届くよりも先に装飾のある細い剣に短剣が払われた。男は後ろに跳ねて距離をとる。男の目の前には、長い臙脂色の髪を揺らした一人の軍人が立ちはだかっていた。ラオネイ王国の赤を基調とする軍服を身に纏った姿に、男は驚きつつも短剣を握り直した。
「赤い髪……! お前がディシュリーか?」
「見ればわかるでしょ。どうしてこんなことをしているのか知らないけど、迷惑になることはしないで」
ディシュリーと呼ばれた軍人は淡々と言い放つ。黒髪が当たり前のため、そうでない髪色はとても目立つ。一目で炎を操ることができる、炎使いだとわかる姿だ。
ディシュリーの姿は少女と呼ぶには大人びているが、大人と呼ぶには幼く見える。名の知れた軍人とはいえ一人、しかも子どもであればまだ勝機はあると考えた男は、口角を上げて重心を落とした。
「手間が省けたぜ、ここで死にな!」
猛撃を仕掛けた男は、手を休めることなくディシュリーを斬りつけようとする。対するディシュリーは、少ない動作で攻撃を弾いてみせた。そして、手の出しようがないことに気づいた男が息をついた瞬間、ディシュリーは大きく一歩踏み出した。花びらのような淡い色の火の粉が男の喉元を掠め、キン、と高い音が響く。ディシュリーの剣は炎を纏い、男が手にしていた武器をディシュリーの背に庇われた自称軍人のすぐ近くに弾き飛ばした。自称軍人はそれをわかっていたのか、驚くことなく短剣を拾い上げた。視線だけでそれを確認したディシュリーは、愛剣に纏わせた炎をそのままに男に言い聞かせる。
「諦めて、すぐに応援が来るから。こんな往来で騒ぎを起こしておいて、私たちが来ないわけないでしょ」
「くそっ」
男は往生際悪く、ディシュリーの背後に回り込もうとした。しかし、男がその場から離れようとするよりも速く、ディシュリーは剣を振るって柄頭で男の腹を殴りつけた。予想だにしなかった攻撃に男は唸りながらその場に倒れ込み、その腕はすぐにディシュリーが携えていた縄で拘束された。
静かに様子を見守っていた住民たちはその様子を確認すると、それぞれ普段通りに過ごし始めた。騒ぎが始まって道行く人を保護していた店からは、この機会に見ていけと商魂を露にしている。ここが街の隅だとは思わせないほどの活気だ。
「シルベート、おつかれ。せっかくの休暇なのについてないわね」
「仕方ないね。こればっかりは目をつぶれないからさ。来てくれて助かったよ」
そう言って自称軍人、もといシルベートは笑った。人の良い笑顔だ。
「怪我はしてないかな?」
シルベートは包丁と短剣を見せないようにしゃがみ、座り込んだままの少年に声をかけた。少年はただ大きく頷いた。
「それは良かった。笛を奪ったとコイツは言っていたけど、左手で握っているそれかな? それは本当に奪ったものなの?」
「……うん。ぼくのものじゃないよ。この人が落としたから、ひろったの」
その言葉にディシュリーとシルベートは目を丸くした。てっきり、男の言い掛かりだと思い込んでいたからだ。
「この人、ふえでツメイヌを呼んでた。おねえちゃんがむこうに追いはらってくれたよ」
少年が指差したのは、ラオネイ王国の西に広がる荒野の方だ。爪狗はすばしっこく、一度敵だと認識すると大きな爪で引き裂こうとしてくる動物だ。荒野で爪狗の群れと戦うのは、手練れでなければ難しい。
「お姉ちゃんはどんな人かな?」
「炎使いのおねえちゃんとおなじ服を着てたよ」
ディシュリーは思わずシルベートに目で確認した。シルベートは真剣な表情で首を縦に振る。行って、の合図だ。
街と荒野の間には、ラオネイ王国が戦時に急きょ造り上げた防衛壁がそびえ立っている。防衛壁によって作られた入りくんだ道を駆けながら、ディシュリーは飛びかかってくる爪狗を剣でいなし、奥へと進んでいる。防衛壁の間であれば爪狗に取り囲まれることはない。日が沈もうとしている中でも爪狗の金色の目は爛々と輝いていて、敵の足を止めようと必死だ。対してディシュリーは、その目を頼りに剣を振るっていた。
次々と仲間を倒された爪狗たちが頭を振って荒野へと逃げていくと、ディシュリーはさらに力強く走った。長い髪が風を受けてなびく。防衛壁を抜ければ国内の西側一面に広がる荒野と対面できる。
最後に立ちはだかった爪狗に一閃入れて壁を抜けたディシュリーは、まず周囲を確認した。荒野とはいえ、十年前に焼き尽くされてから時間が経ち植物も動物も戻りつつある。どこから姿勢を低くした爪狗が襲いかかってくるかはわからない。しかし、予想に反して爪狗は見当たらなかった。替わりに視界に入ったのは、一人の少女だった。
「ディシュリー!」
少女はディシュリーに気づくと、笑顔で駆け寄った。手にしていたダガーはすぐにしまわれる。
「もしかして、前に会った……」
「覚えてる? 三年前に助けてもらった、セルピア。セルピア・ティス。正式にラオネイ王国軍に加えてもらったんだ!」
ぴしりと敬礼をしてみせたセルピアを見て、ディシュリーは思い出した。そして呆れたように言った。
「また爪狗に追われてたの……」
セルピアがラオネイ王国にやってきたのは二年ほど前のことだった。爪狗たちが喧しく吠えているのを聞いたディシュリーが荒野に出てみると、爪狗に対し必死に応戦しているセルピアがいた。救出したところでセルピアが滅亡したギナ王国の生き残りだとわかり、国が保護した。その後セルピアが軍に入ると言って訓練を始めたという噂は軍内部に流れていたが、それを真実だと思っていた人は少ない。
「元気になったようで良かったけど。どうして軍に入ろうと思ったの」
「ディシュリーに伝えないといけないと思って」
再会を喜ぶ明るい表情から一転、セルピアは真剣な表情をした。
「なに?」
「お願い、軍を抜けて。炎使いという存在を、軍事に使わないでほしいの」