炎は静かに燃え続けている。手のひらにあるその白っぽい光源を頼りに、ディシュリーは深い森を進んでいた。昼過ぎに森の入り口からここまで進んできたものの、未だに目的地の村らしき場所は見えてこない。
(今日は野宿かな)
半ば諦め、目についた倒木に座る。ずっと歩いてきたせいか、強い眠気がディシュリーの目蓋を降ろす。無意識に左手を閉じたため、炎はふつりと消えた。このまま寝てしまおうか、と身体の力を抜いたときだった。草木を分け入る音に気づいたディシュリーは反射的に立ち上がり腰に携えた剣の柄を右手で握った。鞘に添えた左手には、微かに炎が灯る。
「誰かいるのかい?」
老いた女性の声を聞いて、ディシュリーは右手を下ろして様子を伺った。声から敵意は感じられない。
しんと静まったままの森に、もう一度声が投げかけられる。
「この辺りは人が滅多に来ないから、動物たちも自由に暮らしているのよ。一人だと危ないわ」
「……私なら大丈夫。訓練はちゃんと受けたから」
本気で心配しているのだと感じたディシュリーは、身を潜めるのをやめた。自分が危ないのであれば、声を出した老婆もまた危険と隣り合わせの状態だ。親切心で声をかけた結果動物に襲われたとなれば軍人として不面目どころではない。老婆を必要以上に驚かせないようにディシュリーは構えていた炎を消し、あえて草木を踏みながら老婆の元へ歩み出た。炎使い特有の赤い髪が、光を受けて暗く光る。
老婆は持っていたランプを掲げてディシュリーを照らし、まあ、とまばたきした。
「軍人さんだったのね。それに、その髪色は……炎使いなのかしら」
「そうだよ。私はディシュリー・ヴォルケイド。おばあさんは星見の村に住んでる人?」
訊きながらも、ディシュリーは老婆の持つランプに灯った火を一瞥した。どことなく自分と似た──使いの──力を感じさせる火は、あたたかな橙色をしている。
「星見の村というのは懐かしい響きねぇ。もう村といえる場所ではなくなってしまったけれど、たしかに村の住人よ。夜に動く任務でなければ、どうぞうちに来てくださいな。ここは寒いでしょう」
「ありがたいけど、私には構わなくていい。ここに炎使いの力を増幅させるものがあると聞いて来たの。心当たりはない? なにか知っていることがあれば教えてほしい」
「使いの力を……? 生憎だけど、うちにあるのは生活と星見のための道具があるくらいでねぇ。そういった類いのものがあるという話も聞いたことはないのよ」
星見とは、言葉の通り空の様子を伺って天候や空の様子を見るものだ。星見の村の住人たちは特にその才に優れ、今のラオネイの天候予測は彼らから知見を得たものだということをディシュリーは知っている。
話ながらもちらりと上空を見やる老婆に対して、手元のランプに灯る炎は微動だにしない。
「……ところで、この灯りは」
「ああ、これかい?」
訊かれた老婆は再度ランプを掲げた。
「この火は昔、貴女のようにこの森に来た人が分けてくれた火でねぇ……獣避けになると言っていたけれど、芯を消費しないばかりか消えもしないの。ずっとこのランプの中で燃えているのよ」
「消えない火……」
「思えばこれは、炎使いがくれた炎なのかもしれないね。使いの力は自然に還ると言うでしょう?」
どこか懐かしむように話す老婆は、おそらく火を分けた人物を思い出しているのだろう。夜の森で暗闇に囲まれているというのに、老婆の表情は楽しげだ。
「もしかしたら、この火が貴女の力になるんじゃないかしら。必要でしたらどうぞお持ちになってくださいな」
そう言うと老婆は躊躇なく、にこやかにランプのグローブを外した。橙の火は芯に触れることなくランプの中に浮いている。その様子をはっきりと捉えたディシュリーは、間違いなくこれが使いの力による炎だと確信した。小さな火だが、受け取れば間違いなく己の一部として昇華できる。
(二代前の炎使いは橙の炎を操っていた、と聞いた覚えがある。……やっぱり炎は死んでも残るのか)
火としばらく向き合ってから、ディシュリーはそこへ左手を伸ばした。ディシュリーの手のひらに現れた小さな炎が転がるように指先を滑り落ちて、橙の火に飛び込んだ。先ほどよりも広い範囲が照らされる。怪訝そうな老婆に、ディシュリーは首を横に振った。
「これは受け取れない。おばあさんにとって大切なものでしょ。それに村に帰るにはランプがないと困るんじゃないの?」
「受け取った貴女から、また火がもらえれば十分よ。それに、ラオネイの状況は決して良くはないのでしょう? 戦力となるなら遠慮しなくていいんだよ」
「遠慮じゃない。私はここに探しに来ただけで、奪いに来たわけじゃないから」
ディシュリーはきっぱり断った。そして早く村に戻ろうと老婆を促す。言外に滲む「この話は終わりだ」という雰囲気に、老婆はそうだねぇ、と曖昧に返事をした。二人はゆっくりと、だがしっかりとした足取りで村へ向けて歩き始めた。もしかしたら、老婆にはディシュリーがあのときの青年に見えているかもしれない。
星と灯り(ディシュリー)
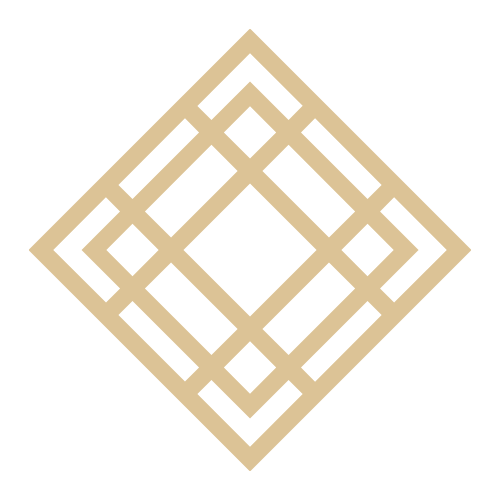 ラオネイ王国の炎使い_小話
ラオネイ王国の炎使い_小話